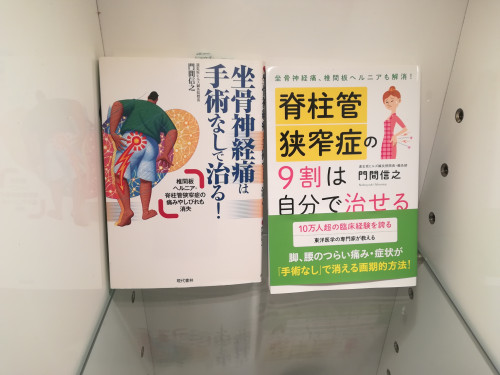ブログ
ジストニア
ジストニア概要
ジストニアは、主動筋と拮抗筋の非協調的な収縮によって引き起こされる運動障害症候群であり、異常な筋緊張と不随意な姿勢を特徴とする。原因によって一次性と二次性に分けられる。前者はDYT1遺伝子の変異に関連することが多く、後者は遺伝性代謝疾患または外因性因子によって引き起こされる。関与の範囲に応じて、局所性、分節性、片麻痺性、全身性に分類される。一般的な臨床症状には、痙性斜頸、捻転性痙縮、メイジュ症候群などがあり、小児期に発症したものは全身症状に進行しやすい。診断は特徴的な運動パターンと異常姿勢に基づいており、頭部CT、代謝スクリーニング、遺伝子検査などの同定技術と組み合わせて行われる[1]。治療にはボツリヌス毒素注射、抗コリン薬、そして重症の場合は脳深部刺激療法(DBS)または視床切開術が含まれます。DBSは、淡蒼球の腹側後面に電極を埋め込むことで神経回路を持続的に調節する治療法です。[2-4]重篤な症例では、呼吸サポート、多剤療法、中西医学の統合治療が必要となる。[5]二次性ジストニアは原疾患を標的とした介入が必要であり、患者の約3分の1は後遺症に悩まされる可能性があります。DBS技術の適用により、正確な標的位置決めによって症状の大幅な改善が達成される患者もいます[3-4]。。
ジストニアは、発生する場所によって、局所性、分節性、片側横隔膜性、または全身性に分類できます。一般的に、発症年齢が若いほど症状が重く、体の他の部位に影響を及ぼす可能性が高くなります。発症年齢が高いほど、ジストニアが局所性のままである可能性が高くなります。局所性ジストニアとは、痙性斜頸、書痙、眼瞼痙攣、口顎ジストニアなど、体の一部のみに影響を及ぼすジストニアを指します。分節性ジストニアは、メージュ症候群 (目、口、下顎)、片方の上肢と首、両下肢など、1 つ以上の隣接領域に影響を及ぼすジストニアです。体の片側に影響を及ぼすものは片側横隔膜性ジストニアと呼ばれ、通常は反対側の大脳半球の病変によって引き起こされます。全身性ジストニアは、少なくとも 1 つの部分と 1 つ以上の他の領域に影響を及ぼします。
病因と病態
原発性ジストニアは、ほとんどが散発性ですが、家族歴のある患者も少数います。遺伝形式は常染色体優性、劣性、X連鎖性で、7歳から15歳までの小児および青年に最も多く見られます。常染色体優性遺伝の原発性捻転痙縮の大部分は、9q32-34に位置するDYT1遺伝子の変異によって引き起こされ、浸透率は30%から50%です。ドーパ反応性ジストニアも常染色体優性遺伝で、グアノシン三リン酸シクロヒドロラーゼ-1(GCH-1)遺伝子の変異によって引き起こされます。フィリピンのパライ島では、X連鎖性劣性遺伝のジストニア-パーキンソン症候群の一種が報告されています。家族性局所性ジストニアは、通常、不完全浸透を伴う常染色体優性遺伝で発生します。
研究では、顔面または歯の外傷歴のある患者において、口腔下顎ジストニアなどの原発性ジストニア遺伝子保有者において、末梢外傷がジストニアを誘発する可能性があることが実証されています。さらに、片肢の過度な運動もジストニアを誘発する可能性があります。例えば、書痙、タイピスト痙、楽器奏者やアスリートの四肢痙など、様々な職業性ジストニアの主な原因は末梢因子であると考えられています。したがって、病因は、脊髄運動回路の再編成、または脊髄レベルより上位の運動感覚接続の変化によって引き起こされる基底核機能の変化に起因すると仮説されています。
二次性(症候性)ジストニアとは、新線条体、旧線条体、視床、青斑核、または脳幹網様体に関わる病変を指し、ジストニア症状の誘発因子となり得る。例としては、肝水晶体変性症、核黄疸、ガングリオシドーシス、淡蒼球黒質変性症、進行性核上性眼筋麻痺、両側基底核石灰化、副甲状腺機能低下症、中毒、脳血管疾患、脳外傷、脳炎、裂脳症、薬剤性ジストニア(L-DOPA、フェノチアジン系薬剤、ブチロフェノン系薬剤、メトクロプラミド、化学療法薬)などが挙げられる。眼瞼痙攣は、背側脳幹虚血や脱髄病変によって引き起こされる可能性があるという報告もある。
病因は不明ですが、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンなどの神経伝達物質の異常濃度が脳のいくつかの領域で報告されていますが、その意義は依然として不明です。最近の研究では、局所性ジストニアは基底核の異常によって引き起こされることが示唆されています。静的画像検査では異常は確認されていませんが、陽電子放出断層撮影(PET)を用いた動的画像検査では、尾状核、レンズ核、そして視床背内側核への前頭葉投射における代謝率の低下が示されています。したがって、基底核と前頭葉間の接続機能障害がジストニアの主原因と考えられています。
臨床症状
捻転けいれん
捻転痙縮は、1911年にオッペンハイム・Hによって初めて命名されました。これは全身性捻転ジストニア、あるいは筋ジストニア(変形性筋ジストニア)を指します。臨床的には、四肢、体幹、さらには全身の激しく不随意なねじれ運動と異常な姿勢を特徴とします。
原因により、原発性と続発性に分けられます。発症は通常5歳から15歳の間に起こります。家族歴がある人では、2代目は1代目よりも若い年齢で発症する傾向があります。患者の60%は遺伝性で、常染色体優性および劣性遺伝がそれぞれ半数を占め、40%は散発性です。発症率は東ヨーロッパ系ユダヤ人で高くなっています。最近の研究では、この遺伝子は9q34にあり、主に3bpのGAC欠失によって引き起こされることが示されている。線条体のドーパミンレベルが低いことは、原発性ジストニアに関連している可能性があります。フィリピンのパナグ島で、X連鎖常染色体劣性型のジストニアが発見されています。このタイプは20代の成人初期以降に発症し、症状は脚や足、または上半身に始まり、患者の50%が全身性疾患になります。
この疾患はあらゆる年齢で発症する可能性があります。小児期発症者は家族歴を有することが多く、症状は片側または両側の下肢から始まることが多く、徐々に広範囲にわたる不随意な捻転運動や異常姿勢へと進行し、重度の機能障害につながります。成人期発症は散発性であることが多く、症状は上肢または体幹から始まることが多いです。患者の約20%は最終的に全身性ジストニアを発症しますが、通常は重度の障害を引き起こしません。
病気の初期段階では、歩行時に片足のつま先が不随意に底屈し、かかとが地面に着かなくなることがよくあります。これは「つま先歩行」と呼ばれます。病気の初期段階では、この異常な動きは前進歩行などの随意運動にのみ影響し、後進歩行や横歩きなどの他の動作には影響しません。これらの動作は完全に正常です。また、片下肢の突然の屈曲や反射性痙攣として現れることもあります。数ヶ月または数年後には、これらの不随意な異常運動は安静時にも発生し、徐々に隣接する四肢に広がり、最終的には顔面、首、そして全身に広がります。顔面の症状は、まばたきやしかめっ面として現れます。舌と喉の症状は、舌の間欠的な伸展と後退、歯ぎしり、構音障害、嚥下障害を伴います。頸部の症状は、痙性斜頸を引き起こす可能性があり、四肢は伸展、屈曲、回内または回外します。体幹および傍脊柱筋の障害により、全身にねじれや螺旋状の運動が生じ、筋肥大、前弯症、側弯症、骨盤傾斜などを引き起こすことがあります。捻転痙縮は、自発的な運動や精神的ストレス時に悪化し、睡眠後には完全に消失します。筋緊張は捻転中に増強し、捻転運動が停止すると正常に戻るか低下するため、変形性ジストニアと呼ばれます。重症例では正常な運動が不可能になる場合があり、進行すると骨格変形や筋拘縮により重度の障害につながる可能性があります。そのため、捻転成分を伴うジストニアは、捻転性痙縮と呼ばれます。
常染色体優性遺伝の家族内では、同一疾患の家族員が複数存在する場合や、眼瞼痙攣、斜頸、書痙、側弯症などの局所症状が複数組み合わさっている場合があり、多くは上肢から始まり、発症部位に限定された症状が長期間持続することがあります。全身型に進行しても症状は比較的軽度です。
捻転痙縮の診断は難しくなく、顔面、首、体幹、四肢、骨盤の奇妙なねじれや不随意運動に基づいて診断できます。様々な原因が除外できれば、一次性捻転痙縮と診断されます。
痙性斜頸
痙性斜頸は、1652年にオランダの医師トゥルピウスによって初めて報告されました。30歳から50歳の患者に最も多く見られますが、小児や高齢者にも発症する可能性があり、男女比は1:2です。頸筋の痙性または緊張性収縮によって引き起こされ、頭部が硬直して回転します。頸部ジストニアは、頭頸部の異常な姿勢につながるため、内因性頸部ジストニアまたは頸部ジストニアとも呼ばれます。
この疾患の病因については長年議論が続いています。患者の5%から10%は、体の他の部位にも軽度のジストニアを呈しますが、これはジストニアの症状の一つと考えられます。この疾患は家族性であることは稀ですが、リウマチ熱、多発性硬化症、神経梅毒、マラリア、一酸化炭素中毒、特定の薬剤、脳炎、甲状腺機能亢進症、ウィルソン病、ハレルフォルデン・スパッツ病などによって二次的に発症することもあります。
典型的な臨床症状には、安静時の急速な頭部回転と断続的または持続的な頭部傾斜があります。成人発症の痙性斜頸は、典型的には非常に緩徐に進行し、最初は不随意に頭部が片側を向くことから始まり、数日または数ヶ月かけて、これらの回転の頻度と振幅が徐々に増大し、同時に間代性けいれん性の痙攣が重なります。深頸筋と浅頸筋の両方が影響を受ける可能性があり、臨床症状は関与する筋肉群によって異なりますが、胸鎖乳突筋、僧帽筋、および頸板筋の異常収縮が最も一般的です。症状が明らかになる前に、不随意にうなずいたり頭を振ったりする患者もいます。痙攣は長くても短くても休止することがあります。重症例では、筋肉が強直的に収縮し、無秩序で激しい動きにより、頭部が継続的に傾斜しねじれますが、回転方向はさまざまです。罹患筋は肥大する可能性があり、これらの不随意運動は感情的な興奮、歩行、または自転車に乗ることで悪化し、仰臥位で軽減し、睡眠中には完全に消失することがあります。不随意収縮を伴う痙性斜頸は頸神経痛を引き起こす可能性があり、重症の場合は腕に放散し、緊張性頭痛を引き起こすこともあります。痙性斜頸は、他の局所性ジストニアよりも疼痛を伴うことが多く見られます。重篤な症状が長期にわたると、頸筋の拘縮や永久的な変形につながる可能性があります。
急性痙性斜頸は、ハロペリドールやメトクロプラミドなどの薬剤反応によって突然発症することがあります。薬剤の服用を中止するか、抗コリン薬やベンゾジアゼピン系薬剤を投与すると、症状は徐々に正常に戻ります。
メージュ症候群
メージュ症候群は、1910年にフランスの医師アンリ・メージュによって初めて記述され、主に眼瞼痙攣と口腔下顎ジストニアを呈します。この症候群は、1) 眼瞼痙攣、2) 眼瞼痙攣と口腔下顎ジストニアの合併、3) 口腔下顎ジストニアの3つのタイプに分けられます。タイプIIはメージュ症候群の完全型であり、タイプIとIIIは不完全です。臨床的には、眼筋と口と顎の筋肉が主に影響を受けます。眼筋の障害は、眼瞼刺激、ドライアイ、羞明、頻繁な瞬きを呈し、進行して不随意な眼瞼閉鎖に至ることもあります。痙攣は数秒から数分間続きます。ほとんどの症例は両眼に発生しますが、少数の症例では片眼から始まり最終的に両眼に影響を及ぼし、読書や歩行に影響を及ぼし、さらには機能的失明につながることもあります。眼瞼痙攣は、精神的ストレス、明るい光への曝露、読書、凝視などによって悪化することが多く、会話、歌唱、口を開ける、咀嚼、笑うことで軽減し、睡眠中には消失します。口腔筋および下顎筋の痙攣は、口を開閉する、ふくれっ面、ニヤリと笑う、唇をすぼめる、舌を突き出す、ねじる、歯をむき出す、食いしばるなどの症状として現れます。重症の場合、顎の脱臼、歯の摩耗や喪失、歯肉の裂傷、舌や下唇の噛み締めなどを引き起こし、発話や嚥下機能に支障をきたすことがあります。痙攣は会話や咀嚼によって引き起こされることが多く、顎に触れたり、オトガイ下部を圧迫したりすることで軽減できます。痙攣は睡眠中に消失します。
アテトーゼ
アテトーゼは、指痙縮または可動性痙縮とも呼ばれ、主に四肢遠位部に生じる、緩慢で屈曲性の蠕動性不随意運動です。下肢が侵されると、母指はしばしば自発的に背屈します。顔面筋が侵されると、患者は顔をしかめ、様々な「しかめっ面」をします。咽頭筋や舌筋が侵されると、患者の発語は不明瞭になり、嚥下困難を呈し、捻転性痙縮や痙性斜頸を伴うこともあります。不随意運動は精神的ストレス時に悪化し、睡眠に入ると消失します。筋肉が痙攣すると筋緊張が高まりますが、筋肉が弛緩すると正常となり、感覚は正常ですが、知能が低下することがあります。この病気の経過は数年から数十年にわたります。極めて緩徐なアテトーゼは、主に四肢近位部、首筋、体幹筋に影響を及ぼし、体幹周囲のねじれが典型的に現れるねじれけいれんに非常によく似た異常な姿勢を引き起こします。
書痙
書痙をはじめとする職業性筋痙攣は、筆記、ピアノ演奏、タイピングなどの作業中に手や前腕の筋緊張障害や異常な姿勢が生じる疾患です。男性に多く、男女比は約2:1です。発症平均年齢は約39歳です。書痙は主に利き手に発症し、右利きの人が多いため、多くの患者は右手に書痙を起こします。患者はしばしば右手で書痙をしますが、他の動作は正常です。書痙の際、患者の腕は硬直し、ペンを短剣のように持ちます。肘は無意識に外側に反り返り、手首と手は曲げられ、手のひらは横を向き、ペンと紙はほぼ平行になります。書痙の性質や職業上、利き手ではない方の手でしか筆記や作業ができない患者もいます。また、この疾患の家族歴がある患者もいます。
診断と鑑別診断
診断
症状の診断は、病歴、特徴的な症状の発現、不随意運動や異常姿勢の部位に基づいて行うことで通常は難しくありませんが、他の類似した不随意運動症状と区別する必要があります。
鑑別診断
(1)捻転けいれんは舞踏病やスティッフマン症候群と鑑別する必要がある:捻転けいれんと舞踏病を鑑別する鍵は、舞踏病の不随意運動が速く、運動パターンが予測できず、異常姿勢が持続せず、筋緊張が低下するのに対し、捻転けいれんの不随意運動は遅く、運動パターンは比較的固定されており、異常姿勢が持続し、筋緊張が亢進することです。スティッフマン症候群は、体幹筋(頸部傍脊柱筋と腹筋)と四肢近位筋の発作性緊張、硬直、固縮を特徴とし、顔面筋と四肢遠位筋は影響を受けないことがよくあります。硬直は患者の能動運動を著しく制限し、痛みを伴うことがよくあります。筋電図検査では、安静時と筋肉が弛緩しているときの両方で持続的な運動単位の電気的活動を示すことができるため、ジストニアとの鑑別が容易です。
(2)痙性斜頸は、頭部振戦や先天性斜頸との鑑別が必要です。先天性斜頸は、若年期に発症し、胸鎖乳突筋血腫後の線維化、頸椎の先天性欠損または癒合、頸筋炎、頸部リンパ節炎、眼筋麻痺(上斜筋麻痺など)などによって引き起こされることがあります。痙性斜頸は、頭部振戦と同様に、発作性の不随意痙攣を呈することが多く、本態性振戦やパーキンソン病との鑑別が必要です。
(3)メージュ症候群は、顎関節症、下顎不正咬合、片側顔面けいれん、神経症と鑑別する必要がある。片側顔面けいれんは、口や下顎の不随意運動を伴わずに、片側の顔面筋やまぶたのけいれんとして現れる。
(4)ジストニアの診断を確定した後は、可能な限り原因を探索する必要があります。一次性ジストニアでは、一般的に振戦以外の陽性神経症状や徴候は見られません。静的ジストニアの発症、早期の異常姿勢の持続、言語機能の早期障害、突然の発症、急速な進行、片側性ジストニアなどは二次性ジストニアを示唆しており、積極的に原因を探索する必要があります。筋痙攣、認知症、小脳症状、網膜変化、筋萎縮、感覚症状などの他の神経症状や徴候を伴う場合も、二次性ジストニアを示唆します。
二次性ジストニアのスクリーニング方法としては、頭部CTまたはMRI(器質性脳損傷の除外)、頸部MRI(脊髄損傷に起因する頸部ジストニアの除外)、血球塗抹標本(神経棘赤血球症の除外)、代謝スクリーニング(遺伝性代謝疾患の除外)、銅代謝測定および細隙灯顕微鏡検査(ウィルソン病の除外)などがあります。小児期発症の捻転性痙縮に対しては、DYTl遺伝子変異スクリーニングも実施可能です。
病気の治療
治療の選択肢には、薬物療法、A型ボツリヌス毒素の局所注射、手術があります。局所性または分節性ジストニアにはA型ボツリヌス毒素の局所注射が適しており、全身性ジストニアには経口薬とA型ボツリヌス毒素の選択的局所注射が適しています。薬物療法またはA型ボツリヌス毒素に反応しない重症例では、手術が考慮されることがあります。
薬物治療
(1)アルタン:アルタンを大量に投与すると、患者の50%に症状がある程度改善しますが、通常は2~6mg/日まで徐々に増量し、その後は1~2週間ごとに2mgずつ増量し、治療効果が満足のいくものとなり、副作用が明らかでなくなるまで続けます。主な副作用は、かすみ目、口渇、便秘などですが、副作用があるからといって増量する絶対禁忌としないでください。副作用が重篤な場合は、増量を1~2週間延期し、副作用が軽減または完全に消失した後に再び増量することができます。一般に、18歳未満の小児の平均耐量は30~40mg/日、最大耐量は80mg/日です。
(2)ドパミン機能を拮抗する薬剤:ハロペリドール:初回は0.5mgを1日1回服用し、その後徐々に1mgを1日3回服用する。症状が十分にコントロールされていない場合は、効果が認められ、副作用が顕著でなくなるまで増量する。チアプリド:1回50~100mgを1日2~3回服用し、症状が改善し、副作用が顕著でなくなるまで徐々に増量する。ピモジド、クロルプロマジン、テトラベナジンなども用いられる。
(3)ベンゾジアゼピン系薬剤:クロナゼパム1~2mgを成人1日3回服用する。ニトラゼパム、ジアゼパムなども使用できる。
(4)カルバマゼピン:成人:0.1~0.2gを1日3回服用。小児:必要に応じて減量する。クロナゼパムまたはハロペリドールとの併用も可能である。
(5)レボドパ:ドパ反応性ジストニアに劇的な効果を発揮する。
ボツリヌス毒素A型注射
(1)眼瞼痙攣:上眼瞼と下眼瞼の中間部と内側部、および中間部と外側部との境界に、眼瞼縁から2~3mm離れた5~6箇所に注射した。5箇所目は、外眼角から1cm離れた、外眼角側頭側の眼輪筋とした。注射後、約90%の患者に中等度または有意な改善が認められた。注射から改善発現までの潜伏期間は4.2日、平均効果持続期間は15.7週間であった。
(2)顎口腔ジストニア:咬筋、側頭筋、外側翼突筋、内側翼突筋、二腹筋を選択し、各筋肉に2~4箇所注射します。重症の場合は、上顎に5箇所注射することもできます。オトガイ下筋にも注射します。治療効果は約50~70%で、効果は3ヶ月持続しますが、患者によっては1年間持続することもあります。副作用としては、嚥下困難、構音障害、咀嚼力低下などがありますが、いずれも一時的なものです。
(3)痙性斜頸:異常な姿勢や動きの原因となる筋肉を正しく特定し、正確な注射部位を特定することが治療成功の鍵です。筋電図検査下で注射するのが最善ですが、筋電図検査下でも検査なしでも注射効果に差がないとの報告もあります。通常注射する筋肉は、胸鎖乳突筋、僧帽筋、頭頸部頬筋、後頸筋、必要に応じて深頸筋です。治療効果は53%~90%で、振戦や筋肉痛などの随伴症状も緩和されます。効果発現時間は3~10日で、3~6か月持続することが多いです。副作用は頸筋の脱力と嚥下障害で、約14%を占め、通常2週間以内に消失します。繰り返し注射すると効果的です。
(4)書痙およびその他の局所性四肢ジストニア:書痙に対して手や前腕の筋肉に注射する場合、筋腹が薄く、筋肉が重なり合っているため、筋電図モニタリング下で終板領域に注射点を選択できれば効果は高くなります。副作用は手の脱力です。局所注射は前腕、足指、体幹などのジストニアにも使用でき、いずれも一定の効果があります。
手術
電気生理学的研究および PET 研究により、ジストニアは淡蒼球-視床-皮質投射系の損傷によって引き起こされることが示されており、これは視床から前頭運動皮質への異常な求心性インパルスをブロックすることでジストニアを治療するという理論的根拠となっています。
(1)視床切開術:薬物治療に反応しない片側性ジストニアに適している。
(2)末梢手術:頸部ジストニアの治療のための末梢手術には、硬膜外選択的後枝切断術、硬膜外前神経根切断術、脊髄副神経微小血管減圧術の3種類がある。
(3)微小電極誘導焼灼術:捻転性けいれんの治療に使用される。
(4)脳深部刺激療法:淡蒼球の腹側後部に単一電極を定位的に埋め込むことで長期間の脳深部刺激を行うと、症状が著しく改善することが研究で明らかになっている。[2]
病気の予後
放送
予後はタイプによって異なりますが、一般的には良性の経過をたどり、数十年にわたり持続します。原発性書痙の症状は非常に安定しており、転移したり悪化したりすることはほとんどありません。患者の約3分の1に障害が生じる可能性があります。
病気の予防
遺伝的背景を持つ疾患では、予防が特に重要です。予防策としては、近親婚の回避、遺伝カウンセリングの促進、保因者検査、出生前診断などが挙げられます。早期診断、早期治療、そして充実した臨床ケアは、患者の生活の質を向上させるために不可欠です。
ジストニアの中国鍼灸は?
鍼治療はジストニアの補助治療として使用でき、神経機能を調整し、局所の血液循環を改善することで症状を緩和するのに役立ちます。ただし、このアプローチには、個々の状態と西洋医学的治療に基づいた包括的な評価が必要です。
I. ジストニアに対する鍼治療の現状 ジストニアは、不随意筋収縮によって引き起こされる運動障害であり、主に異常な姿勢または反復運動として現れます。現在の西洋医学的治療には、主に経口薬(抗コリン剤など)、ボツリヌス毒素注射、および外科手術(脳深部刺激療法など)が含まれます。鍼治療は、伝統的な療法として、筋肉のけいれんを和らげ、痛みを緩和し、運動機能を改善するために臨床診療でよく使用されています。
研究によると、鍼治療は次のメカニズムを介して作用する可能性があります。 中枢神経系の調整:特定の経穴(合谷、太衝、奉池など)を刺激すると、脳の基底核の機能に影響を与え、異常な神経シグナル伝達を阻害することができます。
1. 局所循環の改善:鍼治療は患部の血液循環を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。
2. 神経伝達物質の調節:いくつかの研究では、鍼治療がドーパミンやγ-アミノ酪酸(GABA)などの筋緊張に関連する神経伝達物質のレベルに影響を与える可能性があることが示唆されています。
3. II. 鍼治療の有効性と限界:その補完的役割は明らかです。
1. 軽度から中等度の鍼治療を受けた患者の場合、鍼治療を薬物療法またはリハビリテーショントレーニングと組み合わせると、有効性が向上し、投薬量が減少し、副作用が軽減されます。局所性ジストニア(眼瞼痙攣や書痙など)にはより効果的ですが、全身症状の改善は遅くなります。個人差が大きいです。
2. 有効性は、病気の経過、病因、経穴の選択、および操作テクニックによって左右され、一部の患者では大幅な改善が見られない場合もあります。エビデンスレベルの向上が必要:3. 既存の研究は、主に小規模な臨床試験であり、長期追跡データが不足しています。作用機序はまだ完全には解明されておらず、より質の高い研究が必要です。
III. 推奨される鍼治療計画:経穴の選択:1. 鍼治療は、主に局所経穴(痙性筋の周囲など)と遠位経穴(足三里や陽陵泉など)を組み合わせ、「経絡を浚渫し、陰陽のバランスを整える」ことを重視します。
標準化された手順:2. 鍼治療は専門の鍼灸師によって行われ、刺激を高めるために電気鍼と温鍼法を併用します。治療頻度は通常、週2~3回で、3~6ヶ月間です。併用治療:3. ボツリヌス毒素注射との相乗効果:鍼治療はボツリヌス毒素の作用持続時間を延長し、注射頻度を減らすことができます。リハビリ訓練との併用:筋肉を弛緩させ、協調性を高めることにより、全体的な機能を改善できます。 IV. 注意事項とリスク 根本的な治療法ではありません:鍼治療は主に症状の緩和に使用され、薬物療法や手術の代わりにはなりません。 1. 禁忌:出血性疾患、皮膚感染症、重度の心血管疾患および脳血管疾患の患者は注意が必要です。
2. 定期的な機関を選択する:不適切な操作による感染や針恐怖症などの問題を回避します。 3. V. まとめ ジストニアに対する鍼治療の有効性は個別化されており、包括的な治療の一部として使用できますが、神経科医による評価後に計画を策定する必要があります。患者は合理的な期待を維持し、単一の治療法に盲目的に依存することを避け、同時に現代医学的方法と定期的なフォローアップ訪問を組み合わせて治療戦略を調整する必要があります。